レベル、モノグラム、エアフィクス、フロッグ、オーロラ、リンドバーグ、AMT,MPC,IMC,ジョー・ハン。このうち五つくらいピンとくるようだったら、あなたはかなりのマニアだったはずだ。いや、飛行機のほうだったら四つかな?そう、往年のプラモデル・ブランド名である。AMT,MPC,IMC,ジョー・ハンはクルマ専門だったから、飛行機ばっかり作っていた人には馴染みが無いかもしれない。エアフィクスとフロッグは英国の、他はすべてアメリカのメーカーである。タミヤ、ハセガワ、マルサン、イマイなど、日本のブランド名を出せば、私の世代のほとんどの人がわかってしまうだろうから、あえて輸入ブランドだけ並べてみた。
私は中学に入ったころから高校生になるくらいまで、プラモデル作りにはまった。それはもう、寝ても覚めてもというくらいはまった。一番初めはアオシマかどこかが出していた、一個50円の小さな第二次大戦戦闘機シリーズだったと記憶している。それが小学校五・六年生のことだ。その後、本格的にはまりこみ、たしか中学三年生で自動車に転向するまでは戦闘機一辺倒だった。
プラモデルという呼称はマルサンの登録商標で、一般にはプラスチック・モデルと呼ばれるべきであったが、当時私たちはみなプラモデルでとおしていた。
凝りだすにつれ、”航空情報“や”航空ファン“など、モデル関連のページをもつ雑誌を古本屋で買っては、実物に近付けるための考証にもはまっていった。それらの雑誌には、撃墜王アフリカの星、ハンス・マルセイユや、アルバトロス三葉機を駆るレッド・バロン、リヒトホーフェンの記事などが載っており、戦争の実態に及ぶ想像力をもたない12~3歳の私のロマンチシズムを大いに刺激したものだ。
当時の私の家は古い日本家屋で、個室というものが無く、茶の間と台所にはさまれた二畳のスペースに勉強机を二つおき、私と弟の勉強部屋と称していた。とはいえ、私にはその部屋で何か勉強らしきことをした記憶が全く無い。机の上はいつも作りかけのモデルと制作ツールが取り散らかっていた。
住まいは横浜だったが、通った中・高校は東京にあったので、次第に輸入プラモを扱う店に頻繁に出入りすることになる。新橋にあったステーション・ホビーと、もう一軒、名前を忘れてしまったが代々木に専門店があった。1/48サイズのものは当時で大体1500円以上して、一月の小使いが1000円だった私にはなかなか手が届かなかったので、主に1/72サイズが私の制作の中心となっていた。当時その精密な作りで知られたモノグラムには1/72シリーズは無く、レベルとエアフィクスが主体で、それでも4~500円していたと思う。ハンブローという英国製のエナメル系塗料が具合がいいという評判で、私も少しずつステーション・ホビーで買い揃えていった。とても小さな缶にはいっていて、一色確か150~200円もした。それぞれの色に英空軍何とかとか、米軍何とかという色名がついていて、いかにもオーセンチックな感じがしたものだ。確かに絵の具の伸びもよく、マットの仕上がりも綺麗だった。
初めて買ったモノグラムの1/48製品はP-51ムスタングBで、発売当時大変評判になったキットだ。私はこれを1967年に買っている記録があるので、多分発売は1966~1967年にかけてのことだろう。その頃には私の小使いも毎月1500円に上がっていたように記憶している。それでもこのキットはもう少し高かったはずで、お年玉か親父のボーナス時におねだりでもしたのだろうが、はっきりした記憶が無い。この前年あたりにレベルのジェット戦闘機A3Jヴィジランテをお年玉で買った。空母の甲板から今にも飛び立とうとしている美しい箱の絵にワクワクしたものだ。お年玉というのは当時の子供にとっては大変な財源で、ご近所や親戚から毎正月一万円近いお金が入る。そのすべてが、私の場合モデル制作に消えていった。この1967年にもう一機、モノグラムのP-40Bを作って私の戦闘機制作は終わっている。


自動車モデルに入っていく前段に、レベルから出ていた、エド・ロスのラット・フィンクがあった。どうも記憶が錯綜としていて、もしかして始めての出会いはプラモ制作に凝りだして早々のころかもしれないのだが、確か東京駅の大丸のおもちゃ売り場でのことだ。これには本当にびっくりした。キャラクター自体にも驚いたが、それがモデル・キットとして出ていることに更に驚いた。それまでの自分の世界とはまったく異質の、とんでもない新しい世界にめぐり合ったような気がした。ドラグナット、マザーズ・ウォリーなどがシリーズで並んでいたと思う。値段も割りと安く、300円くらいだったのではないだろうか。ラット・フィンクと、もう一つ二つ作ったはずだ。
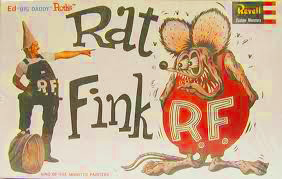
車のモデルに入っていった最初はモノグラムのクラシック・カー・シリーズで、デュセンバーグとロールスロイスを作った。かなり高いキットで、それぞれ2400円くらいだったと思う。飛行機から自動車に移っていった理由はハッキリとは思い出せないのだが、ひとつにはこれらのアメリカ製自動車キットの精密さだったと思う。外観だけでなく、エンジンからトランスミッションまで入っているのだ。これは当時の日本製の自動車キットには無かった。もう一つおぼろげに思い出されるのが、航空情報などを買っていた古本屋でカー・グラフィック(雑誌)にも親しんだことで、名前を忘れてしまったが、毎号でていた或るイラストレーターの素晴らしいクラシック・カーのイラストに心底魅せられた。カッチリと最後まで塗り込まず、未完成として完成されたそれらのイラストは、えもいわれぬ気品と風格があふれ、自分の今住む世界をひと時忘れさせてくれる素晴らしいものだった。 今また見れないものかとネット上を検索しまくったのだが、イラストレーターの名前もわからない状態なので見つけることができなかった。何となく英国の画家だったような気がするのだが、どなたかご存知の方がいたら教えていただければ幸いである。
ステション・ホビーの狭い店内の、入って右側の棚の中段以上はギッシリと自動車キットの箱で埋まっており、そこに並ぶホット・ロッドやドラッグ・スターに親しむのに時間はかからなかった。なにしろ多くのキットが“3 in 1”という形式で、ストック、カスタム、ドラッグ仕様のいずれかに作れるように余分のパーツが入っているのだ。これにはモロにはまった。いくつか買い続けると、自然と余分のエンジンやインテリアのパーツが手元に溜まってくる。それを利用して、キットに無い自分独自のカスタム・カーを作り出すようになる。レベルからは、エンジンだけ、或いはタイヤだけの小さなパーツ・キットも出ていた。店の左側下段にはモデル関連の輸入雑誌が並べてあり、モデル・カー・サイエンス、カー・モデルといったアメリカのモデル・マガジンが入っていた。ホット・ロッド・マガジンなどの実車雑誌も在ったように思う。AMTからは、本物のカスタム・カーに使われるようなメタル・フレイクやキャンディー・カラーのスプレー塗料も出ていて、正面のレジの脇に並べてあった。車の1/24スケール・キットは大体2000円くらい、雑誌やスプレー塗料が確か一つ300円だったから、幾ら小使いやお年玉をつぎ込んだと言っても、当時の中学生がパカパカ買えるものではない。実は入ってすぐ右にバーゲン品が積み上げられており、いきおい私の買い物はそこが中心となっていた。どうも、あまり人気の無い、在庫として一定期間残ったものが廻されていたようで、定価の半額だった。品質としては全く問題のないもので、私のようにどうせ勝手に作り変えてしまうモデラーにとってはまさに宝の山であった。

 自作のカスタム・カー
自作のカスタム・カー
私にとってのモデル制作は、もちろん一つ一つのパーツを組み上げて完成したモデルを作ることは楽しかったのだが、それ以上に、作っているあいだ、戦闘機であればその実物が大空を駆け巡っているイメージ、車であればそれが実際に走り回っている世界に浸りこめることが嬉しかった。その世界は勿論私が幼い想像力で勝手にこしらえたもので、前記したように、たとえ戦闘機であっても現実の戦争の悲惨はスッポリと抜け落ちていて、淡い憧れとロマンチシズムにあふれていた。車に関して言えば今ひとつの事情が絡まってもいたように思う。丁度、車のモデルに夢中になりだした頃から、洋楽(ポップ・ミュージック)にもはまり込んでいっていたからだ。
記憶にある、私が初めて魅かれたポップ・ミュージックはパーシーフェイス楽団の”夏の日の恋“(A Summer Place)である。映画の発表は1959年、テーマ曲のヒットは1960年で、1961年度のグラミー賞を獲得しているから、私はまだ8~9歳、ということは実際に聞いたのはしばらく後のことなのだろう。爽やかなストリングスにのせた甘い旋律は、見たことの無いアメリカという国への憧れをかきたてた。小学校中学年くらいの頃には”ビーバーちゃん“や”ディズニー・ランド“をみていたし、高学年の頃にはアンディ・ウィリアムズ・ショーもテレビで放映されていて、彼の歌う”モア“や”カナダの夕陽“に、アメリカと言う国の豊かさ、おおらかさを夢見ていた。”サーフサイド 6”も、その主題歌と共に忘れられない番組の一つだ。今思えば、1960年代のアメリカ芸能界、ひいてはアメリカという国自体に、それなりの猥雑さといかがわしさが見えるのだが、当時の私はそこへ届く想像力も人生経験も無く、ただただその爽やかさ、豊かさ、カラフルで自由奔放な世界に魅せられていた。
中学二年生の頃には、チョット外へ買い物に出るにもラジオを持っていくほど洋楽にはまりきっていた、ちょうどシナトラの”夜の訪問者“(Strangers In The Night)、シュプリームスの”恋は急がず“(You Can’t Hurry Love)、ハプニングスの”シー・ユー・イン・セプテンバー“(See You In September)などがチャートを賑わせていたころだ。当時はビルボードとキャッシュ・ボックスのチャートが約一月遅れで日本に入ってきていた。もちろんビートルズやストーンズも入ってきていたし、シルビー・バルタンなどのフランスものもあり、私も好きだったが、それら洋楽すべてをひっくるめて、西洋=アメリカと思わせる強さが私の中のアメリカにはあった。

これらのヒット曲が醸し出す世界は、私の中でホット・ロッドやカスタム・カーのそれと地続きに存在していた。モンキーズが登場し、モンキー・モービルがモデル・キットとして発売されたのはもう少し後のことだが、確かモデル・カー・サイエンスに、“スター達のカスタム・カー“みたいなタイトルで何ページかの記事が載ったことがある。現実のスターが乗っている車ということではなく、このスターにはこんなカスタム・カーをというデザイン画の特集みたいなものだった。ほとんど忘れてしまったが、シュプリームスのためにデザインされた車がスマートかつゴージャスで、今でも何となく思い出すことが出来る。ビーチ・ボーイズがホット・ロッド好きで、ホット・ロッド関連の曲を集めたアルバムを出していることを知ったのはもうしばらく先のことだった。
レベルがカラー写真をふんだんに使った豪華なカタログを出していることを知って、矢も楯もたまらずに、たどたどしい英語で手紙を書き、アメリカの本社に注文を入れたのもこのころのことだ。どのように支払いをしたのか憶えていないが、一月以上かかって本当にそのカタログが届いた時は嬉しかった。約50ページにわたって、組み上げられたモデルがすべてカラー写真で載っており、思っていた以上の素晴らしさに、私のアメリカに対する敬愛の念は深まった。
モデル・カー・サイエンスには“モデル・オブ・ザ・マンス”という読者の自作カスタム・カーを紹介するコーナーがあって、注目を浴びたモデルの作者には25ドルの賞金が与えられることになっていた。自分の作ったカスタム・カーにはそれなりの自信もあったし、当時の25ドルは日本円で9000円である。なんどか応募してみようかと思ったが、幾ら写真で見て自分もイケそうだと思っても、日本人が作ったものなど本場の人達が相手にしてくれないだろうという疑念に打ち負かされて、一度も応募しなかった。今思えば、日本人の、しかも中学生だからこそ注目をあびたに違いないのに、まったく残念なことをしたものだ。9000円あれば、ステーション・ホビーのバーゲン・キットがなんと9個も買えたのに!
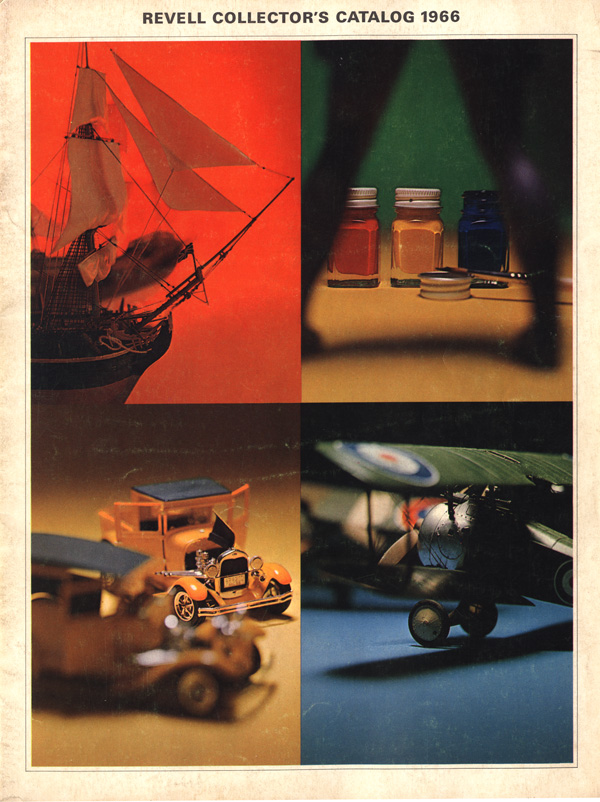 Revell 1966 カタログ |
 Model Car Science Mar.1966 |
私がモデル制作にのめり込んだのは勿論制作自体が楽しかったことに間違いないが、もう一つの大きな理由は、今思えば現実からの一種の逃避だったからに違いない。当時の私達家族が住んでいたような日本家屋にはプライバシーと言えるようなものは一切無かった。すべての仕切りはふすまと障子で、四畳半の茶の間が居間兼食堂、となりの六畳で父母と私と弟が川の字になって寝、奥の六畳に祖父祖母が寝るようになっており、私が小学校四年生の時に祖父が死んでからはその六畳は祖母の部屋となっていた。あとは私と弟が勉強机を並べていた二畳に、同じく二畳サイズの台所と便所、これがすべてである。まわりの家も皆似たようなもので、それぞれの家が夕飯に何を食ったかまで、知りたくなくてもわかってしまうのだ。私の家では母と祖母の折り合いが悪く、つねに暗い雰囲気がただよっていた。こうした環境のなかでアドレッセンスの入り口に立った私には、育ち上がって来る自意識の置き場がなかった。少なくとも無いように思えた。モデル制作と、それにまつわる想像の世界は、私の自意識に恰好の逃げ場を提供してくれたのだろう。モデルを作っている間、カタログやモデル雑誌に読みふけっている間、ポップ・チューンに聞き入りながら次のモデルに思いを馳せている間、私は自分がこしらえた想像の世界に浸りきって、周りの現実をシャット・アウトすることが出来た。
私が生まれたのは1952年で、その前年には日米講和条約が締結され、日本は少なくとも政治的には米国の占領から脱しているが、私が受けた教育は、終戦後の占領下、GHQの指導のもとに施行された民主主義教育そのままといっていいだろう。確かに、私は近代日本がたどった軍国主義への道や、天皇制下の日本社会について、学校で教わった記憶は無い。しかし同時に、いかにアメリカによって与えられた民主主義が素晴らしいかと教わった記憶も無い。まあ、義務教育で教えられることに一般教養以上を望むのもおかしなものだとは思うが、そんなこと以前に、アメリカ生まれの大衆文化はガッチリと日本の子供達の心を掴み取っていたのだ。私の世代の男の子で、“ちびっこ大将“、”三馬鹿大将“、”名犬ラッシー“、”名犬リンチンチン“、”ローン・レンジャー“、”ララミー牧場“、”宇宙家族ロビンソン“などのアメリカ製テレビ番組を、一つも見ずに育った者がいるとは思えない。当時の日米の為政者達がどこまで意識的であったかはわからないが、メディアを通じて私達の生活に入り込んできたアメリカ大衆文化は、占領終了後の日本人に、他のどのような政策以上に強力な影響力を及ぼしたと言っていいだろう。
あれからほぼ半世紀、私がアメリカに移り住んでからは20年近い年月がたち、当時思い描いていたアメリカが私の頭の中にだけ存在した幻想であると理解する今でも、その輝きは失せることがないのである。